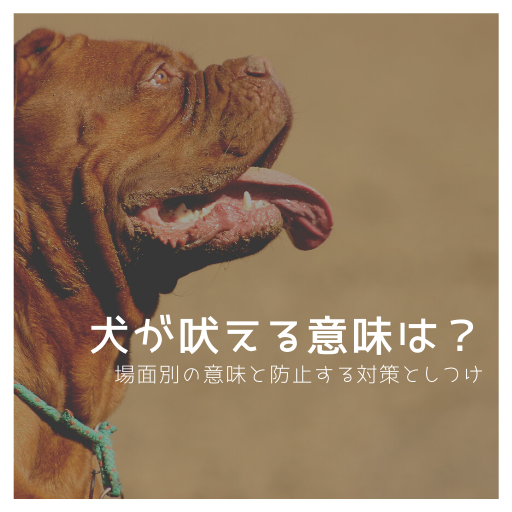犬の感情は豊かで、性格によってもさまざまな吠える意味があります。
一見うるさいと思ってしまいますが、それぞれ吠える意味があるのです。そこで、犬が吠える意味をまず理解しましょう。意味を理解し、それに合わせた対策としつけをしてみると効果的です。
犬が吠える意味:シーンや吠え方によって意味が異なる

犬は何らかの要求をしているときに吠えます。代表的なものからあげていきます。
要求で吠える:家族に対して吠えるのは優位性を示している
家族に対して犬が吠えるのは、優位性を示しています。犬自信が、何かを欲しいとき、何かをしてほしいとき、思い通りにならないときに、家族に対して吠えます。これは、吠える相手に対して優位性を示しています。
「優位性を示す」ということは、犬自信が「相手の人よりも優位な立場にある」と思っているからです。
犬は、家族の中で序列を作ります。序列とは、一番偉い人が誰か、同等はだれか、自分より偉くないのは誰か、といった順位のことです。
たとえば、お父さん、お母さん、子供の3人家族で犬を飼っている場合、犬自信が、この3人家族の中で序列を決めているのです。
- 1番偉い人=リーダーと思っている人:お父さん(世話をする、えさをくれる)
- 同等の人=リーダーの次の人:お母さん(散歩につれてってくれる)
- 自分=犬自信
- 自分より下の人=子供(友達。遊んでくれる人)
この序列でいくと、自分より下の人に対して吠えます。つまり、自分より上の人には吠えません。
恐怖で吠える:怯えたり、怖いと思っている
何かにおびえたり、怖いと思って恐怖で吠える場合は、
・来客に対して吠える
・玄関チャイムの音が鳴ると吠える
・外で人に向かって吠える
などがあります。
来客や玄関チャイムの音に対して吠えるのは、未知=よく知らない人に対する恐怖で吠えています。
また、外で人に向かって吠える場合も同じで、急に触ろうとした人に吠える、大きな声を出す人に吠える、子供など動きの予測がしづらい人に吠えるのも、基本的には怯えや恐怖で吠えています。
恐怖で吠えているときは、しっぽを下げて、耳を並行より下に下げて吠えます。
威嚇で吠える:縄張りを侵された、自分より下の人に威嚇
威嚇で吠える場合は、自分の縄張りを侵されたと感じた時、または自分より序列が下の人や動物に対して吠えます。
この場合は、前出の通り「怯えや恐怖」で吠えている場合とは逆に、しっぽをたてて、耳をぴんとたてています。加えて、歯茎を出して「怒っている顔」をしていることもあります。
来客に対して吠える場合は、縄張りを侵されたと感じます。郵便屋さんや配達員に吠えるのはこのケースです。番犬のように、自分の縄張りを守る意識から吠えています。
ドッグランで気が合わない犬に吠えたり、子供等にしつこくちょっかいを出されて吠えるのは、自分より下のものに対して「やめて」と威嚇の意味で吠えています。
遠吠え:犬の本能、仲間に呼応している
遠吠えはオオカミの本能で、オオカミの血を継ぐ犬も遠吠えをすることがあります。ペットで日常的に遠吠えをすることは少ないといわれています。ただし、救急車のサイレンや、17時のチャイムの音に反応して遠吠えをしたりします。
遠吠えの意味は、仲間の遠吠えに対して呼応しているといわれています。遠吠えが聞こえたら、こちらも遠吠えを返し、自分の縄張りの場所・距離感を知らせています。
遠吠えは、同族の犬に対してのコミュニケーションとして使われているのです。
また、寂しいときや不安なときも遠吠えをすることがあるといわれています。
認知症で吠える:脳の老化、自律神経の乱れ
犬も認知症になります。7歳を過ぎると、認知症のリスクが高まるといわれています。認知症の犬は、夜泣きをしたり、吠え続けたりすることがあります。認知症の場合の吠え方の特徴として、「抑揚がなく一定のリズムで吠え続ける」といわれています。
認知症によって吠える場合は、不安感が強い、病気による痛みや不快感、分離不安、ストレス、警戒心などです。
認知機能の低下により、不安耐性、ストレス耐性は低くなり、警戒心は強くなります。つまり、我慢したり制御したりすることが難しくなります。なので、若いときには吠えなかったのに、少しの不安やストレスで吠えやすくなったり、警戒することがないのに神経質になって吠え続けたりしてしまうようになります。
痛みで吠える:何かケガをしたり病気などで痛みがある
ケガによる痛みや、病気による痛みなどで吠える場合があります。その場合は、何かの動きの拍子に「キャン!」「キャイーン!」と鋭く吠えます。また、椎間板ヘルニアや関節炎など断続的な痛みの場合は、吠える感覚も断続的になります。痛みが強いと「ギャイン!」といった悲痛な吠え方になることもあります。
人や動物に対して吠えるのではなく、鋭い吠え方をする場合は、ケガや病気による痛みの可能性がありますので、速やかに病院で診てもらったほうがいいでしょう。犬は言葉が話せない上に、我慢強い性格の子が多いので、痛みを訴えるのはかなり症状が進んでいる可能性もあるので、少しの異変にも気づいてあげましょう。
犬が吠える意味に合わせた対策
犬が吠えるのには色々な意味があることがわかりましたよね。それでは、その意味やケース別の対策をあげていきます。

要求で吠えている場合の対策:犬との信頼関係を築く
犬はもともと群れで行動していて、リーダーに従う習性があります。このことを「主従関係」ということもありますが、そもそも主従関係といった難しいことではなく、まずは信頼関係を築きましょう。
主従関係というと、呼び戻し(名前を呼んだらこちらに来させる)やマテ、フセなどのコマンドが聞けるかどうか、といったことで判断されるといわれています。
しかし、そもそも愛玩犬やペットとして飼っているのであれば主従関係といった「主の指示に従う」しつけがすべてとは言えない、といった考えがペット先進国では生まれています。つまり、犬を人間の思うがままにいいなりにさせる必要はないとの考えです。
それよりも、飼い主のことを信頼できると犬から思われるようになると、犬との信頼関係ができ、要求吠えはしなくなります。
信頼関係を築くためには、まずは「犬が飼い主といると嬉しい」と思わせる行動をしましょう。しつけもそれに従って、「良いことをしたらほめる」ようにし、「悪いことをしたら怒る」ことをやめます。同時に、悪いことをしづらい環境を作ることもとても大事です。
恐怖で吠えている場合:怖がる必要がないことを教える
犬が吠える意味の中で、未知のものに対する「恐怖で吠える」場合は、怖がる必要がないことを教えてあげます。
といっても、言葉で言ってもわかりません。「大丈夫だよ、〇〇さんだよ」とか「宅配屋さんだから吠えなくてもいいよ」となだめたくなりますが、犬は日本語を文章レベルで理解することはできません。
そこで、具体的には、来訪者(お友達などの来客や、郵便屋さんなど)がきたら、おやつをあげましょう。これを習慣化することで、来訪者=おやつをもらえる、ということをインプットしていきます。
来訪者が友達や家族の場合は、その人にも協力してもらいましょう。具体的には、おやつをあげてもらうようお願いをし、愛犬がおやつを食べたらほめてあげましょう。
そうしていくうちに、来訪者は「敵ではない」と認識し、成功体験を積んでいくことで徐々に警戒して吠えることが少なくなっていきます。
おやつをあげてもらうことが難しかったり、ダイエット中のときは、犬好きの人であれば、愛犬に対して
- 声をかけてもらう
- 名前を呼んでもらう
- 手のにおいをかがせてもらう
でも十分効果があります。
すぐに打ち解ける性格の子であれば、すぐに耳を少しさげて喜ぶことでしょう。こうして、小さな成功体験を積んでいく努力をしてみてください。
すでに成犬になってしまっていると子犬期より吠え癖が身についてしまっているかもしれませんが、根気強く飼い主さんと一緒に努力することで、覚えられないことはありません。
愛犬はあくまで、不必要とはいえ「怖い」気持ちになってしまっています。怖がってしまっている愛犬に対し、怒ったり怒鳴ったりしたら余計かわいそうですし、そもそも問題解決になりません。愛犬のためにも、飼い主さん自身のためにも、一緒にがんばりましょう。
縄張りを侵された威嚇で吠えている場合:他の指令を出す
縄張りを侵されたため、威嚇で吠えるのは、ある程度仕方のないことです。これはオオカミ時代からの本能であり、自分の縄張りを守るための必死の訴えなのです。
大事なことは、縄張りを侵されて吠え続けているときに飼い主さんが制御できることです。
例えば、呼び戻しをして、愛犬をこちらに呼んだり、名前を呼んでこちらを向かせてボール遊びをしかけたり、縄張りを侵され吠え続けることから「気をそらしてあげる」ことで回避します。
本能を阻止するのは難しいので、飼い主さんが現代社会で愛犬が生きやすいように導いてあげることも重要です。
犬が縄張りとして認識しているのは、家にいる場合、家の敷地内かと思います。巣穴は自分のベッドだったり、クレートとなります。
敷地内に入ってきたとき、縄張りを侵す対象とはまだ距離があるはずです。近づく前に、気をそらしてあげましょう。そのために、
- アイコンタクト
- 呼び戻し
などだけでも覚えておくと、愛犬との意思疎通が図りやすいです。
吠え続けると、「吠えるモード」いわゆる興奮状態になってしまい、もっと収拾が難しくなっていきます。
犬が吠えた時:吠え続けさせる前にコマンドで気をおさめてあげる
犬が吠え続けると興奮状態やパニック状態に近い状態となり、飛び掛かりやケガのリスクが高まります。そうなる前に適切にコントロールしてあげましょう。

まずは、吠え続けそうになる前に、「ワン!」と一回でも吠えたら、続けて吠えないように、気をそらすようにしてあげましょう。
呼び戻しができるようであれば、名前を呼んでこちらにこさせる、窓の外が気になるようであれば、別の部屋に移動するようにコマンド等で支持を出して連れてってあげる、など、興奮状態を作らないように、環境を整えてあげましょう。
犬のコマンドの代表的なもので、
- 吠えろ=speak(スピーク)
- 静かに=quiet(クワイエット)
があります。これは、吠える指示と静かにする指示で、一般的にセットで教えるコマンドです。
私の場合は、あまり多くのコマンドを教えるしつけをする方針ではないので、静かにしてほしいときには
- シー!(口元に人差し指をたてるジェスチャーと一緒に)
と教えました。吠えるコマンドは教えていません。
この練習法は簡単で、
- シー!と言って一瞬こちらに意識が向いたときに、すかさずほめてご褒美
を繰り返すだけです。これは、どんな時でも簡単に使えて、大きな声を出したくないような環境でも、今では慣れてジェスチャーだけでも理解をしてくれています。
肝心なのは、一回目に「ワン!」と吠えた時に、すかさず「シー!」とコマンドを出すこと、そして一瞬静かになったらすぐに褒めること、です。タイミングを逃さないことが非常に重要です。そして、コマンドを理解できるようになるまでは、繰り返しできるようになるまで練習します。
コマンドで重要なことは、
- いつも同じ声のトーンで
- いつも同じ言い方にする
ことです。犬は、子音が聞き取りづらく、母音をメインに聞き取っているといわれています。また、声色やトーンで人間の感情を読もうとしているので、コマンドを出すときは、低めの同じトーンで、同じ言い方に統一することが重要といわれています。
認知症や痛みで吠えているとき:なるべく早く病院に相談を
認知症や、痛みで吠えているときは、コマンドやしつけで制御するものではないので、速やかに病院に相談することをお勧めします。
認知症であれば、興奮や攻撃性を抑えることが難しくなっているので、落ち着きをもたせるサプリメントや薬を処方してくれることもあります。
また、ケガや病気で痛みによって吠えている場合は、原因を特定し治療をしなければならいので、なるべく早く先生に診てもらってください。